会計士の試験科目の中に経営学があって、その中のマーケティング論を学んでいます。
試験委員の一人ということもあり、この教授の本が紹介されていました。

- 作者: 恩蔵直人
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞社
- 発売日: 2004/11
- メディア: 新書
- 購入: 6人 クリック: 139回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
今日はマーケティング用語のSTPについて。
STPは、Segmentation, Targeting, Positioningの略。
マーケティングを展開するにあたって市場全体に対してやみくもに販売するのではなく、市場をいくつかのセグメントに分け、自社にとって有利な部分を選んで、そのターゲットに対して明確なブランドポジションを規定すべきことをいう。
1.セグメンテーション
市場全体に対するマーケティングをマス・マーケティングというのに対して、市場をいくつかに分けることをミクロ・マーケティングという。
ミクロ・マーケティングはさらに、セグメント・マーケティング、ニッチ・マーケティング、カスタマイズド・マーケティングの3つに分かれる。
セグメント・マーケティングでは、市場をいくつかのセグメントに分けてそれぞれにあわせた製品やサービスを提供する。
ニッチ・マーケティングは、市場において明確なサブ・ニーズを有した小さな特定部分に対して行うマーケティングである。
カスタマイズド・マーケティングは、顧客一人ひとりに対して行うマーケティングであり、ミクロ・マーケティングの究極の姿である。
2.ターゲティング
市場をセグメントに分けたならば、自社が狙う市場を設定しなければならない。
この標的市場を定めることをターゲティングという。
ターゲティングはさらに、無差別型マーケティング、差別化型マーケティング、集中型マーケティングの3つに分かれる。
無差別型マーケティングとは、市場セグメント間の違いを無視して共通の製品やサービスを提供する考え方をいう。
ニーズの相違点ではなくニーズの共通点に着目した、いわばマス・マーケティングに近いといえる。
差別化型マーケティングとは、複数のセグメントに対してそれぞれ違った製品やサービスを提供する考え方をいう。
セグメントAには製品Aを、セグメントBには製品Bを販売するという具合である。
集中型マーケティングとは、特定のセグメントに注目してそこに自社の経営資源を集中させようとする考え方をいう。
よく言われる選択と集中ということ。経営資源の比較的少ない中小企業がとりやすいマーケティングといえよう。
ただし、環境が変化しその市場が不振になったりしようものなら一気に経営も不振になってしまうリスクを抱える。
3.ポジショニング
ターゲットとすべきセグメントを見つけたならば、その市場において自社が占めるべきポジションを明確にしなければならない。
これは絶対的なものではなく、競合他社との比較の中で位置づけられる相対的なものであり、製品に対するものではなく、顧客の心理に対して働きかけるものである。
自社からの働きかけがないと顧客に勝手にポジショニングされてしまう恐れがあるため、有効な切り口でのポジショニングが求められる。
有効なポジショニングの条件としては、重要性、独自性、優越性の3つがあげられる。
ポジショニング戦略において陥りがちなミスとして、アンダーポジショニング、オーバーポジショニング、混乱したポジショニングの3つがある。
アンダーポジショニングは、切り口が不適切であるためイメージが薄くなってしまうこと。
オーバーポジショニングは、焦点の設定が不適切なためブランドポジションを狭く捉えられてしまうこと。
混乱したポジショニングは、ブランドポジションが固定せず混乱させてしまうこと。
以上見たように、STPはマーケティングを展開するにあたって最優先に取り組むべき重要課題だといえよう。

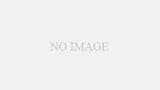
コメント